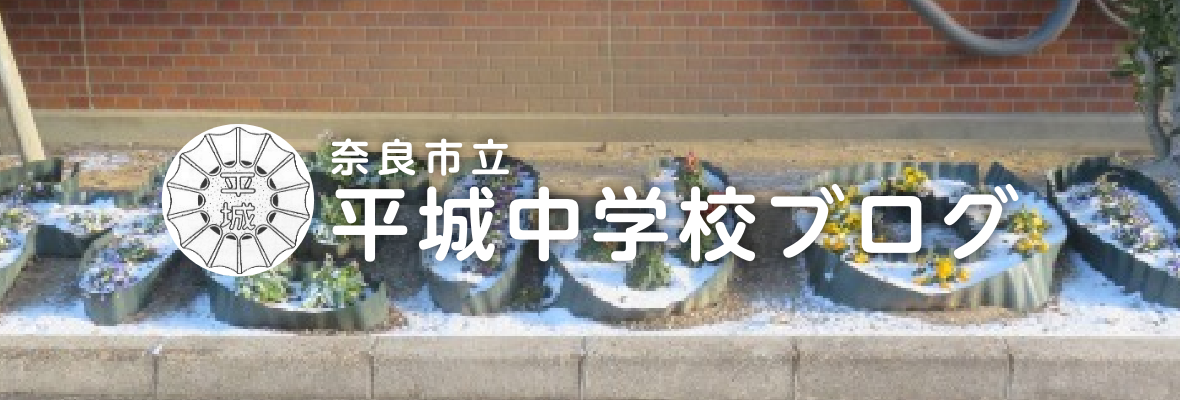7月11日 木曜日 給食58回目
パン・牛乳・肉だんご・こんにゃくラーメン・にんじんしりしり
今日は「こんにゃく麺」の話をします。今日のラーメンに入っている麺はこんにゃくで作られています。こんにゃく麺は小麦粉で作られた普通の麺とは違い、時間がたっても伸びないのが特徴です。また、こんにゃく麺に使われているこんにゃくにはおなかの調子を整えてくれる食物せんいがたくさん入っています。よくかんでいただきましょう。
7月10日 水曜日 給食57回目
ご飯・牛乳・タコライス・スライスチーズ・ボイルキャベツ・かきたまスープ
今日は「タコライス」の話をします。「タコライス」はメキシコのタコスという料理が由来です。タコスの具材のひき肉・チーズ・レタス・トマトをご飯にかけて食べる沖縄で生まれた料理です。本場メキシコではピリ辛のカレーに似たような味ですが、今日はみなさんが食べやすいようにアレンジした味になっています。ご飯の上にボイルキャベツ・タコライスの具を乗せ、その上にちぎったスライスチーズを乗せてタコライスを完成させていただきましょう。
7月9日 火曜日 給食56回目
パン・牛乳・フィッシュアンドチップス・キャベツのソテー・ガーリックスープ・黒豆きなこクリーム
今日は、「ガーリックスープ」の話をします。ガーリックスープは、にんにくを風味豊かなスープに仕上げた料理です。ガーリックはにんにくのことで、当時にんにくは薬として食べられていました。その後、ヨーロッパで調味料として使われ始めました。庶民の間でにんにくを使った料理は夏バテ予防にもなることから、スタミナ料理として食べられていました。ヨーロッパで古くから食べられてきた「にんにく」を使ったガーリックスープを味わっていただきましょう。
7月8日 月曜日 給食55回目
ご飯・豚肉の塩こうじ炒め・奈良漬きんぴら・じゃがいものみそ汁・大和茶カップケーキ
今日は、「古都ならの日」です。奈良市で作られたお米をよりおいしく味わうために、地場産物や郷土料理を取り入れた献立が登場します。奈良漬はその名の通り奈良県が発祥の伝統食品です。塩漬けにした野菜を酒かすに漬けた漬物です。白瓜で作られたものが有名ですが、なすやきゅうり・すいかなどでも作られています。今日は、奈良漬をきんぴらに入れています。また、大和茶を使った大和茶カップケーキもついています。奈良県のおいしい食材を味わっていただきましょう。
7月5日 金曜日 給食54回目
ご飯・牛乳・さばの甘辛焼き・茎わかめの炒めもの・七夕汁・七夕ゼリー
今日は、「七夕献立」の話をします。七夕は、「年に一度、7月7日の晴れた夜に天の川で彦星と織姫が会える日」といわれています。今日の給食は、天の川に見立てた「そうめん」と、星に見立てた「オクラ」を入れた「七夕汁」です。オクラは、夏が旬の野菜で、切り口が星の形に見えるのが特徴です。また、星の形をしたゼリーが入っている七夕ゼリーもついています。七夕にちなんだ献立を楽しくいただきましょう。
7月4日 木曜日 給食53日目
パン・牛乳・野菜コロッケ・ラタトゥイユ・ミネストローネ・いちごとりんごのジャム
今日は、ラタトゥイユに入っている「ズッキーニ」の話をします。夏が旬のズッキーニは、見た目はきゅうりに似ていますが、かぼちゃの仲間です。フランス料理やイタリア料理の食材として知られていて、実と花のどちらも食べられます。日本へは、40年ほど前から出回り、現在では主に宮崎県や長野県で作られています。今日は、夏野菜と一緒にオリーブ油やガーリックで煮込んだ「ラタトゥイユ」に入っています。元気に過ごすために残さずいただきましょう。
7月3日 水曜日 給食52回目
ご飯・牛乳・ビビンバ・トックスープ
今日は「ビビンバ」の話をします。ビビンバは韓国料理の一つです。韓国料理は、たっぷりの野菜・にんにく・ごまなど体によい食品を取り入れ、医食同源の考えに沿ったものが多いです。医食同源とは、日頃からバランスの取れた食事をとることで病気を予防しようという意味の四字熟語です。今日のビビンバは日本でもなじみのある料理ですが、韓国では「ビビンパ」と発音します。「ビビン」が混ぜるという意味で、「パ」がご飯です。また、トックスープも韓国料理の一つです。今日は韓国料理のビビンバとトックスープを味わっていただきましょう。
7月2日 火曜日 給食51回目
パン・牛乳・ハンバーグのケチャップ煮・ポテトサラダ・コーンスープ・キャンディチーズ
今月のめあては、「夏の食生活について考えよう」です。暑い夏を元気に過ごすために、気をつけることが三つあります。一つ目は、「朝・昼・夕の食事をきちんと食べましょう」です。特に、一日の元気のもとになる朝ごはんが大切です。二つ目は、「冷たいものを食べすぎないようにし、のどがかわいたらお茶や牛乳を飲みましょう」です。三つ目は、「好き嫌いしないでバランスのよい食事をしましょう」です。毎日の給食も残さず食べて、元気に過ごしましょう。
6月28日 金曜日 給食50回目
ご飯・牛乳・いわしのかんろ煮・かやくご飯の具・かぼちゃのみそ汁
今日は、「かやくご飯」の話をします。「かやくご飯」はごぼうなどの野菜や油揚げ・肉などの具材を加えて炊き込んだご飯のことです。全国的には「炊き込みご飯」や「五目ご飯」と呼ばれることが多いですが、関西では「かやくご飯」や「色ご飯」とも呼ばれています。米を節約するために、さまざまな具を混ぜて炊いたことがはじまりといわれています。家庭によって入れる具材に違いがあり、それぞれの家庭の味になります。また、冷蔵庫に残った野菜などを加えることで、食材を無駄にせずおいしく食べることができます。ご飯に混ぜてかやくご飯を完成させ、おいしくいただきましょう。
6月25日 火曜日 給食49回目
黒糖パン・牛乳・ゴーヤチャンプルー・春雨スープ・シークワーサーゼリー
今日は、6月23日の「沖縄慰霊の日」にちなんだ献立です。ゴーヤチャンプルーは沖縄県の郷土料理です。「チャンプルー」には、沖縄の方言で「ごちゃ混ぜ」と言う意味があり、家庭でも手軽に作られる炒め物です。ゴーヤは、きゅうりと同じウリ科の仲間で、食べると苦い味がするため「にがうり」とも呼ばれています。この苦み成分には、暑さで弱った体をシャキッとさせる効果があり、体の調子を整えるビタミンも多く含まれています。今日は、沖縄県の特産品である「黒糖」を使った「黒糖パン」や沖縄県のかんきつ類「シークワーサー」を使ったゼリーも登場します。沖縄県の料理を味わっていただきましょう。
6月24日 月曜日 給食48回目
ご飯・牛乳・きびなごのレモンじょうゆあえ・青菜の煮びたし・豚汁
今月の「食育の日」の献立は、「鹿児島県」の郷土料理を紹介します。鹿児島県は日本有数のきびなごの産地として知られています。きびなごは帯状の模様がある小さな魚です。鹿児島県南部の方言で帯のことを「きび」、小魚のことを「なご」と呼ぶことから、きびなごと呼ばれるようになりました。今日は衣をつけて油で揚げ、レモンじょうゆとあえています。豚肉や野菜がたっぷり入った「豚汁」は、みなさんにもなじみのある家庭料理ですが、実は鹿児島県の郷土料理でもあります。味わっていただきましょう。
6月21日 金曜日 給食47回目
ご飯・牛乳・コーンしゅうまい・奈良のマーボーなす・わかめスープ・キャンディチーズ
今日は、「マーボーなす」の話をします。マーボーなすは日本でアレンジされた中国の四川料理で、なすとひき肉を使った料理です。日本では、マーボー豆腐と同じ味付けで、豆腐のかわりになすを使って作られます。なすは夏が旬の野菜で、スポンジのような果肉でひき肉のうまみを含みおいしくなります。今日は、奈良県で作られた新鮮な「なす」を使っていて、ピリッとした味が夏にぴったりのメニューです。味わっていただきましょう。
6月20日 木曜日 給食46回目
パン・牛乳・フランクフルトのケチャップあえ・じゃがいもとツナの炒め物・米粉マカロニのミネストローネ・奈良のブルーベリージャム
今日は、「米粉マカロニ」の話をします。「米粉マカロニ」には、奈良県産のお米を粉にした米粉を使っています。米粉は、いろいろな料理やお菓子に使われます。米粉マカロニは、普通のマカロニと比べて「もちもち」とした食感で、主に体を動かすエネルギーになる食べ物です。今日は、星の形をした米粉マカロニをたっぷりの野菜と一緒に煮込みミネストローネにしています。「奈良のブルーベリージャム」もついています。パンと一緒に残さずいただきましょう。6月19日 水曜日 給食45回目
ご飯・牛乳・ちくわの大和茶揚げ・きらずの煮物・にゅうめん
今日は、奈良県の地場産物の話をします。「ちくわの大和茶揚げ」に使われている「大和茶」は、弘法大師が中国から茶の種を持ち帰り、現在の宇陀市で育てたことがはじまりだと言われています。奈良市では朝晩の気温差が大きい月ヶ瀬・都祁・柳生・田原などの大和高原を中心に栽培されています。大和茶はすっきりとした味で、香りがとてもよいです。最近では、飲むだけでなく、いろいろな料理に使われるようになってきました。今日は、ちくわの衣に大和茶の粉を混ぜて揚げています。そして、「きらずの煮物」と「にゅうめん」は奈良県で昔から食べられてきた郷土料理です。味わっていただきましょう。
6月18日 火曜日 給食44回目
米粉パン・牛乳・奈良大豆のポークビーンズ・ごぼうサラダ・冷凍みかん
今日は、「大豆」の話をします。日本は、世界でも大豆をよく食べる国として知られており、豆腐や納豆・みそ・しょうゆ・油揚げなどさまざまな食品に加工され食べられてきました。また、大豆には肉と同じくらいのたんぱく質が含まれていることから『畑の肉』とも呼ばれています。今日の「ポークビーンズ」には奈良県産の「サチユタカ」という大豆がたっぷり入っています。残さずいただきましょう。
6月17日 月曜日 給食43回目
ご飯・牛乳・新じゃが煮・片平あかねちりめん・納豆
今日は、「片平あかね」の話をします。片平あかねは、奈良市の隣にある山添村の片平地区で古くから作られている「大和の伝統野菜」です。根の先まで細長く皮が赤いのが特徴です。寒い時期になると食べ頃になりますが、収穫の時期が11月から12月と短いので、甘酢漬けにして保存します。今日は甘酢漬けにした片平あかねとちりめんじゃこを炒めた「片平あかねちりめん」です。そして今週は奈良県の食材を積極的に取り入れた「地産地消ウィーク」です。地元の味に親しみながら、味わっていただきましょう。
6月14日 金曜日 給食42回目
ご飯・牛乳・豚肉となすの甘辛煮・チンゲン菜のごま炒め・中華スープ
今日は、「チンゲン菜」の話をします。チンゲン菜は、1970年代頃に中国から日本に伝わってきました。シャキシャキとした食感とくせのない味で、熱を加えることでほのかな甘みを感じることができます。気温の変化に強い野菜なので、北は北海道から南は沖縄県まで、全国各地で栽培することができます。今日は、ビタミン・カリウム・カルシウムなどの栄養素がたくさん含まれているチンゲン菜を、ごまと一緒に炒めています。おいしくいただきましょう。
6月13日 木曜日 給食41回目
パン・牛乳・野菜コロッケ・キャベツのソテー・かぼちゃのポタージュ・棒ソーセージ
今日は、「かぼちゃ」の話をします。かぼちゃは、夏が旬の緑黄色野菜です。中が濃い黄色やオレンジ色をしているのは、カロテンという栄養素がたくさん含まれているからです。カロテンは、体の中に入ってビタミンAになり、病気から体を守る働きがあります。また、かぼちゃには体の疲れをとるビタミンCやおなかのそうじをしてくれる食物せんいも含まれています。今日は、栄養たっぷりのかぼちゃを使った「かぼちゃのポタージュ」です。残さずいただきましょう。
6月12日 水曜日 給食40回目
ご飯・牛乳・豚肉のしょうが炒め・切り干し大根のピリ辛炒め・豆腐のみそ汁
今日は、「豚肉のしょうが炒め」の話をします。豚肉には、体をつくるたんぱく質のほか、体の疲れをとるビタミンB1が多く含まれています。そして、しょうがには、血液の流れをよくする働きがあります。豚肉をしょうがで炒めると、それぞれに含まれている栄養素の働きがパワーアップします。また、しょうがの独特な風味や香りは豚肉の臭みを消し、料理の味を引き立てます。暑くなって食欲の落ちる時期にピッタリの料理ですね。味わっていただきましょう。
少しピリッとしておいしかった。
6月11日 火曜日 給食39回目
パン・牛乳・ハンバーグのてり煮・チーズポテト・トマトとレタスのスープ・みかんジャム
今日は、「レタス」の話をします。レタスは、地中海沿岸・西アジア原産の野菜です。一般的によく売られている玉レタスやサニーレタス、サラダ菜などいろいろな種類があります。シャキシャキとした食感が特徴で、サラダやハンバーガーなどで生のまま食べられることが多い野菜ですが、最近では炒め物やスープなどの料理にも使われるようになってきました。旬のレタスを使ったスープを味わっていただきましょう。
6月10日 月曜日 給食38回目
ご飯・さばの梅煮・吉野煮・奈良なすのみそ汁・ミニたい焼き
今日は「古都ならの日」です。奈良市で作られたお米をよりおいしく味わうために、地場産物や郷土料理を取り入れた献立が登場します。吉野煮には吉野地方で作られた「吉野くず」が使われています。くず粉は、植物のくずの根に含まれるでんぷんを粉にしたものです。日本料理や和菓子などに使われ、くず粉でとろみをつけることで、料理を冷めにくくししたり、体を温めたりする効果があります。また、吉野くずの他に、さばの梅煮の梅ペーストや、みそ汁のなすも奈良県で作られたものを使っています。奈良県のおいしい食材を味わっていただきましょう。
6月7日 金曜日 給食37回目
ご飯・牛乳・ガパオ・ビーフンスープ・杏仁豆腐
今日は、「ガパオ」の話をします。「ガパオ」はタイ料理の一つで、一つの料理に塩味・酸味・甘味・辛味などがバランスよく入っているのがタイ料理の特徴です。「ガパオ」の正式な料理名は「パッガパオ」といいますが、「パッ」が「炒める」、「ガパオ」が「バジル」という意味があります。本場ではバジルのほかにも、オイスターソース・唐辛子・カタクチイワシなどの魚を発酵させて作った「ナンプラー」という調味料で、ひき肉を甘辛く炒めて作ります。給食ではナンプラーのかわりにしょうゆを使い、唐辛子は入れずに、食べやすく仕上げました。ご飯と一緒に味わっていただきましょう。
しっかりとした味でおいしかった。
6月6日 木曜日 給食38回目
減量パン・牛乳・和風スパゲティ・ツナとひじきのサラダ・いちごヨーグルト
今日は、「ひじき」の話をします。ひじきは海そうの仲間で、春から夏にかけてが旬で、この時期に採れたものは、やわらかくておいしいです。収穫したての生のひじきは、そのままだと渋みがあり食べられないため、煮てから干して乾燥させます。そして、食べる時に水で戻して、煮物や炒め物などにします。ひじきには、骨や歯を丈夫にする働きのあるカルシウムや、おなかの調子を整える働きのある食物せんいが豊富に含まれています。今日は、ツナ・キャベツ・にんじん・コーンと一緒に「サラダ」にしています。マヨネーズをかけて、味わっていただきましょう。
6月5日 水曜日 給食35回目
ご飯・牛乳・ししゃもフライ・きんぴらごぼう・えのきたけのみそ汁
今日は、「かみかみ献立」です。「ししゃもフライ」の話をします。ししゃもは体長15cmほどの魚です。骨まで丸ごと食べることができるので、魚介類の中でもカルシウムを多くとることのできる魚のひとつです。また、カルシウムの吸収を助けるビタミンDも多く含まれているので、成長期のみなさんにピッタリな食材です。今日は、丸ごと食べやすいようにパン粉をつけて揚げています。残さずいただきましょう。
シシャモフライサクサクでおいしかった。
6月4日 火曜日 給食34回目
パン・牛乳・チンジャオロース・かきたまスープ・ミルククリーム
今月のめあて「よくかんで食べよう」の話をします。なぜよくかむとよいのか知っていますか? 一つ目は、食べ物をしっかりかむと、食べ物が細かくなって、消化がよくなるからです。二つ目は、歯やあごがじょうぶになるからです。三つ目は、あごや口の筋肉を動かすので、脳への血の流れがよくなり脳の働きを活発にしてくれるからです。また、6月4日から10日は「歯と口の健康週間」です。よくかんでいただきましょう。
かきたま、チンジャオロースとパン?
6月3日 月曜日 給食33回目
ご飯・牛乳・ポークカレー・コールスローサラダ・福神漬
今日は、「カレー」の話をします。インドで生まれたカレーは、19世紀にイギリスに伝わりカレー粉が誕生し、その後日本に伝わってから、独自に変化した料理といわれています。奈良市の学校給食では、バターを溶かし小麦粉を加え、時間をかけ茶色になるまで炒め、さらに、カレー粉を加えて作った手作りのルウを使っています。今日のポークカレーにも、たくさんの種類の材料が使われており、おいしくなるようにと調理員さんが思いをこめて作っています。残さず感謝していただきましょう。
5月31日 金曜日 給食32回目
ご飯・牛乳・そぼろどんぶりの具・青菜の煮びたし・豆腐のみそ汁
今日は、「そぼろどんぶり」の話をします。みなさんは「そぼろ」がどんなものか知っていますか。そぼろは、豚肉・鶏肉・牛肉のミンチや、魚・えび・たまごなどをパラパラになるまで炒め、味をつけたものです。そのままご飯にのせたり、おにぎりの具にしたりします。今日のそぼろは、豚肉のミンチと細かく切ったごぼう・にんじん・土しょうがを炒め、甘辛く味つけしました。上手にご飯にのせて、そぼろどんぶりにしていただきましょう。
5月30日 木曜日 給食31回目
パン・牛乳・肉だんご・春雨のスープ煮・牛乳プリン
今日は、「春雨」の話をします。みなさん、春雨は何から作られているか知っていますか。春雨は、緑豆やじゃがいも・さつまいものでんぷんから作られます。春雨は中国で生まれ、日本には鎌倉時代に伝わってきたとされています。でんぷんから加工し乾燥させた春雨は、そのままでは食べられないので、水で戻してから加熱し、煮物や炒め物にしたり、春雨サラダなど和え物にしたりして食べられます。今日はスープ煮にしています。食感を楽しみながらおいしくいただきましょう。
5月29日 水曜日 給食30回目
ご飯・牛乳・新じゃが煮・野菜炒め・手作りふりかけ
今日は、「新じゃがいも」の話をします。新じゃがいもは、3月頃から九州を中心に出回ります。そして、収穫できる場所は日本列島を南から北へと移っていき、6月頃まで続きます。新じゃがいもは、ふつうのじゃがいもと比べて皮が薄く、水分が多くてみずみずしいことが特徴です。じゃがいもにはビタミンCが多く含まれていますが、収穫してすぐに食べる新じゃがいもには、さらに多く含まれています。豚肉・玉ねぎ・にんじん・糸こんにゃくと一緒に煮込んだ「新じゃが煮」を味わっていただきましょう。
5月28日 火曜日 給食29回目
パン・牛乳・アスパラ入りクリームシチュー・海そうサラダ・チョコクリーム
今日は、「グリーンアスパラガス」の話をします。グリーンアスパラガスは、4月から6月が旬の、筆のような形をした野菜です。最近ではよくお店に並んでいますが、江戸時代にヨーロッパから日本に伝わってきた当時は、見て楽しむ鑑賞用でした。グリーンアスパラガスは体の調子を整えるビタミンや疲れをとるアスパラギン酸を多く含んでいます。今日はクリームシチューに入っています。おいしくいただきましょう。
5月24日 金曜日 給食28回目
ご飯・牛乳・いわしのしょうが煮・キャベツのごま炒め・豚汁
今日は、「キャベツ」の話をします。キャベツは40枚から50枚ぐらいの葉が重なって球のように大きくなります。そのように成長するのは、葉にしっかりと水分を蓄えるため、そして太陽の強い日差しから花の芽を守るためだと言われています。今日の給食に使っているキャベツは、「春キャベツ」と言います。春キャベツは、葉の巻きがふんわりとしていてやわらかく、シャキシャキとした食感があるのが特徴です。旬の春キャベツを使った「キャベツのごま炒め」をおいしくいただきましょう。
5月23日 木曜日 給食27回目
パン・牛乳・ヒレカツ・青菜のソテー・コンソメスープ
今日は、「コンソメスープ」の話をします。「コンソメスープ」はフランスで食べられるようになり、その後、世界中に広まっていったと言われています。「コンソメ」はフランス語で、「完成された」という意味があります。肉や魚・野菜などをコトコト煮ることで、旨味が溶け出した澄んだおいしいコンソメスープになります。今日は、ベーコン・玉ねぎ・にんじん・じゃがいもが入ったコンソメスープです。野菜の旨味を感じながら味わっていただきましょう。
5月22日 水曜日 給食26回目
ご飯・牛乳・豚肉のしょうが炒め・にんじんちりめん・もやしのみそ汁
今日は、クイズをします。私の名前は何でしょう?
ヒント1:給食には毎日のようにでます。
ヒント2:根の部分を食べています。
ヒント3:うさぎや馬も大好きな食べ物でオレンジや赤色をしています。
・・・・・・(間をおく)・・・・・・
わかりましたか? 答えは、にんじんです。今日は、豚肉のしょうが炒めとにんじんちりめんに使っています。にんじんには、病気に負けない体を作るカロテンが多く含まれています。残さずいただきましょう。
5月21日 火曜日 給食25回目
パン・牛乳・ハンバーグのケチャップ煮・ポテトサラダ・コーンスープ
今日は、「ハンバーグ」の話をします。ハンバーグは、ドイツのハンブルクで作られたことからハンバーグと呼ばれるようになりました。ひき肉とみじん切りにした玉ねぎにパン粉を混ぜ、塩を加えて肉の粘りを出し、卵をつなぎにして焼いて固めます。和風ハンバーグ、煮込みハンバーグ、照り焼きハンバーグ、豆腐ハンバーグなどいろいろな種類があります。今日はケチャップ味のハンバーグです。残さずいただきましょう。
5月20日 月曜日 給食24回目
減量ご飯・牛乳・ちくわの天ぷら・和風カレーうどん・鶏レバーの煮付け
今日は、「和風カレーうどん」の話をします。カレーうどんは明治37年頃に東京のそば屋で初めて作られ、全国に広まったといわれています。洋食店でカレーが人気になり、お客さんを取り戻すには何か新しいことをしなければと考えられ、誕生したのがカレーうどんです。今日の和風カレーうどんは給食室でだしをとり、肉や野菜を煮て、カレー粉と調味料で味をつけ、少しとろみをつけて仕上げています。おいしくいただきましょう。
5月17日 金曜日 給食23回目
ご飯・牛乳・かて飯の具・みそポテト・すまし汁
今日は、「食育の日」の献立です。5月は、埼玉県の郷土料理が登場です。かてめしの「かて」とは野菜や山菜・きのこなどのことです。米の生産量が少ない秩父地方を中心に、味付けをして煮た「かて」をご飯にまぜて量を増やして食べたことから、「かて飯」ができたといわれています。「みそポテト」は、収穫したじゃがいものうち、小ぶりなものをいろりで焼き、みそダレをぬって食べたのが始まりとされています。農家では、農作業の合間に食べられてきました。今では日常のおかずやおやつとして食べられています。埼玉県の郷土料理を味わっていただきましょう。
5月16日 木曜日 給食22回目
パン・牛乳・チャプチェ・わかめスープ・杏仁豆腐
今日は、「チャプチェ」の話をします。チャプチェは、韓国の伝統的な料理の一つで、「チャプ」は、混ぜ合わせる、「チェ」は、おかずという意味があり、細切りにした野菜・肉・きのこなどを春雨と炒め合わせ、甘辛く味付けした料理です。韓国では、「食べるものはすべて薬になる」といった考え方があります。食を大切にしている韓国の食卓には、ご飯・スープ・主菜・副菜そしてキムチが必ず並び、日本と同じように栄養バランスの良い食事だと言われています。今日は、韓国料理を味わっていただきましょう。
5月15日 水曜日 給食21回目
ご飯・牛乳・ポークカレー・ごぼうサラダ・福神漬
今日は、「ポークカレー」の話をします。給食のカレーは人気の献立で、そのおいしさの秘密は三つあります。一つ目は、カレールウをバターと小麦粉から手作りしていることです。二つ目は、二種類のカレー粉を使っていることや、かくし味にヨーグルト・ケチャップ・リンゴピューレ・チャツネなどを使っていることです。三つ目は、何と言ってもたくさんの量の肉や野菜を大きな鍋で、ゆっくり時間をかけて煮込んでいることです。今日は、豚肉を使ったポークカレーです。味わっていただきましょう
5月14日 火曜日 給食20回目
減量パン・牛乳・大和茶クリームスパゲティ・ツナとひじきのサラダ・フルーツキャロットゼリー
今日は、「大和茶クリームスパゲティ」の話をします。大和茶は、806年に空海というお坊さんが、昔の中国からお茶の種を持ち帰り、奈良の宇陀に伝えたことが始まりとされています。月ヶ瀬や都祁、田原など、朝晩の気温差が激しく、きれいな水が流れる自然豊かな奈良県の大和高原を中心につくられています。5月上旬は、お茶が旬の季節で、その年の春につんだ「新茶」が出回ります。新茶は香りがよく、うま味がつまっています。今日は、クリームスパゲティに大和茶の葉を入れました。お茶の風味を感じながら、味わっていただきましょう。
5月13日 月曜日 給食19回目
ご飯・牛乳・マーボー豆腐・ワンタンスープ・魚ふりかけ
今日は、「マーボー豆腐」の話をします。マーボー豆腐は、1860年頃に誕生した中華料理です。中国の四川省に住んでいたチンさんというおばあさんが、家にある材料でお客さんに作ったのがはじまりだと言われています。辛味をつける調味料は“そらまめ”と“唐辛子”で作った「トウバンジャン」で、マーボー豆腐には欠かせない調味料です。ピリッと辛いマーボー豆腐をおいしくいただきましょう。
5月10日 金曜日 給食18回目
ご飯・牛乳・にしんのかんろ煮・きんぴらごぼう・じゃがいものみそ汁
今日は、「きんぴらごぼう」の話をします。きんぴらごぼうの「きんぴら」は、昔話で有名な金太郎の子ども「坂田金平」からつけられました。金平は、金太郎のように力持ちで、金平に勝てる人は誰もいないといわれるほど強かったことから、強いものの例えとして、「きんぴら」という名前が使われるようになりました。しっかりとした歯ごたえのあるごぼうを千切りにして甘辛く炒めた料理を「きんぴらごぼう」というようになりました。よくかんでいただきましょう。
5月9日 木曜日 給食17回目
パン・牛乳・チキンメンチカツ・切り干し大根のナムル・五目スープ
今日は、「切り干し大根のナムル」の話をします。ナムルは、韓国の家庭料理の一つで、もやしやほうれん草・ぜんまいなど旬の野菜や山菜を塩ゆでし、調味料とごま油であえたものです。韓国ではおかずとして数種類のナムルを食卓に登場させるので、たくさん野菜を食べることができます。今日の給食は、切り干し大根と小松菜が入っています。切り干し大根は、大根を細切りにし、太陽の下に干してつくります。干すことにより甘みが増し、シャキシャキ感が出ます。また、骨をつくるカルシウムや血をつくる鉄分も多くなります。残さずいただきましょう。
5月8日 水曜日 給食16回目
ご飯・牛乳・タコライス・ボイルキャベツ・もずくスープ・スライスチーズ
今日は、「沖縄料理」の話をします。「タコライス」は、タコスの具材のひき肉・チーズ・レタス・トマトをご飯にかけて食べる、沖縄で生まれた料理です。今日の給食では、タコライスの具とボイルキャベツをご飯の上にのせてタコライスを完成させましょう。また、「もずくスープ」のもずくは海そうの仲間で、日本で食べられているほとんどが沖縄県で収穫されています。もずくの表面のぬめり成分には、胃腸を元気にし病気にかかりにくくする働きがあります。栄養たっぷりの沖縄料理を食べて元気に過ごしましょう。
5月7日 火曜日 給食15回目
揚げパン・牛乳・コーンしゅうまい・こんにゃくみそラーメン
今日は、「揚げパン」の話をします。揚げパンは昭和30年頃に給食にはじめて登場し、50年以上続く人気メニューです。揚げパンの日にパンが袋に入っていないのは、給食室で調理員さんがひとつひとつていねいにパンを揚げ、砂糖をまぶして作っているからです。パンを揚げる作業はとても大変ですが、みなさんの喜ぶ顔を思い浮かべながら一生懸命揚げています。調理員さんの思いがこもった給食の揚げパンを味わっていただきましょう。
5月2日 木曜日 給食14回目
パン・牛乳・ポークビーンズ・コールスローサラダ・棒ソーセージ
今月のめあては、「食事のマナーを守ろう」です。みなさんは食事をする時のいろいろなマナーを知っていますか?「いただきます」「ごちそうさま」は、食べ物の命や作ってくれた人々に感謝の気持ちをあらわす言葉です。心を込めて挨拶をしていますか?食器は正しく並べていますか?食事の時に大声で話をしたり、ひじをついたりしている人はいませんか?みんなで楽しく食事ができるようにするためにも、周りの人への心遣いは大切なマナーです。正しいマナーを身につけ、残さずにいただきましょう。
5月1日 水曜日 給食13回目
ご飯・牛乳・ちらしずしの具・若竹汁・柏餅・きんし卵
今日は、「柏餅」の話をします。5月5日は「こどもの日」で、「端午の節句」ともいわれています。こどもの日には、兜やこいのぼり・五月人形を飾り、子どもの幸せや健康を祝う日として柏餅を食べます。柏餅は、米粉から作った餅で「あん」をくるんだものを柏の葉で包んでいます。柏の葉は、新しい芽が出るまで古い葉が落ちないところから、家族がいつまでも繁栄しますように、という願いが込められています。また、ちらしずしと若竹汁も、子どものすこやかな成長を願って食べられる行事食の一つです。食べ物に込められた意味を考えながら、味わっていただきましょう。
4月30日 火曜日 給食12回目
パン・牛乳・揚げぎょうざ・野菜炒め・中華スープ
今日は、「チンゲン菜」の話をします。チンゲン菜は、今から約50年前に中国から日本に伝わってきました。シャキシャキとした食感と、くせのない味で、熱を加えることでほのかな甘みを感じます。気温の変化に強い野菜で、北は北海道から南は九州まで、全国各地で栽培することができます。また、ビタミン・カリウム・カルシウムなどの栄養がたくさん含まれています。今日は、チンゲン菜の他にも玉ねぎ・にんじん・えのきたけ・青ねぎなどたくさんの野菜が入った中華スープです。おいしくいただきましょう。
4月26日 金曜日 給食11回目
ご飯・牛乳・さば飯の具・すろっぽ・ふのみそ汁
毎月19日は、食育の日です。昨年度に引き続き、「給食で全国味めぐり」と題して、日本の様々な地域の郷土料理が食育の日に登場します。今月は和歌山県の郷土料理です。みかん栽培が盛んな和歌山県那賀地方では、みかんの収穫が終わると、みんなでさばの炊き込みご飯を食べます。海から離れている地域なので、塩さばを使うのが特徴です。「すろっぽ」は、和歌山市南部でたくさん採れる、大根・にんじんなどの野菜を無駄なくおいしく食べる方法の一つとして生まれました。すろっぽという名前は、大根・にんじんを千六本に突いた料理「せんろっぽん」がなまって、「すろっぽ」と呼ばれるようになりました。和歌山県の郷土料理を味わっていただきましょう。
4月25日 木曜日 給食10回目
減量パン・牛乳・野菜のかき揚げ・かやくうどん・ブルーベリージャム
今日は、「野菜のかき揚げ」の話をします。かき揚げは、野菜や魚介類などの材料を小さく切ったものを、小麦粉で作った衣でまとめ、油で揚げた日本料理の一つです。材料をかき混ぜて揚げることから「かき揚げ」と呼ばれるようになりました。そのまま食べたり、天つゆや塩をつけたり、いろいろな食べ方をします。今日のかき揚げは、調理員さんが一つ一つていねいに揚げています。かやくうどんにのせて食べてもおいしいですよ。
4月24日 水曜日 給食9回目
ご飯・牛乳・にしんのかんろ煮・鶏肉とたけのこの煮物・じゃがいものみそ汁・のりのつくだ煮
今日は、「たけのこ」の話をします。たけのこは、春を代表する食べ物で、「竹」の「子ども」のことです。寒い冬が過ぎ、暖かくなり始めると、竹林の地面から頭をのぞかせぐんぐんと大きくなります。その成長はとても早く、わずか10日ほどで竹になります。堀りたてのたけのこは、とてもやわらかくておいしいです。春が旬のたけのこを味わっていただきましょう。
4月23日 火曜日 給食8回目
黒糖パン・牛乳・春キャベツと新じゃがのシチュー・ごぼうサラダ・フランクフルトのケチャップあえ
今日は、「春キャベツと新じゃがのシチュー」の話をします。今日の給食に使っているキャベツは、春に採れたものなので、「春キャベツ」といいます。春キャベツは、葉の巻きがふんわりとしていてやわらかく、葉はシャキシャキとした食感があるのが特徴です。新じゃがいもは、収穫後すぐに出荷されるため、皮が薄くみずみずしいのが特徴です。じゃがいもには、病気に負けない体を作るビタミンCが多く含まれています。今日は旬の春キャベツと新じゃがいもが入ったシチューです。黒糖パンと一緒においしくいただきましょう。
4月19日 金曜日 給食7日目
ご飯・牛乳・新じゃが煮・あさりのしぐれ煮
今日は、「あさり」の話をします。あさりは、海の浅い所にいて、砂浜をあさってとるところから「あさり」と名付けられました。あさりには、血液のもとを作る鉄分という栄養が多く含まれています。血液は、私たちの体の中で少しずつ新しく作りかえられています。鉄分をとることで、貧血予防になり元気に過ごすことができます。今日はしぐれ煮にしています。健康を考えていただきましょう。
4月18日 木曜日 給食6回目
パン・牛乳・ビーンズドライカレー・こふきいも・米粉マカロニのミネストローネ
今日は、「米粉マカロニのミネストローネ」の話をします。ミネストローネは、野菜をたくさん使ったイタリアのスープです。地域や季節によって使う材料や作り方がいろいろある家庭料理です。ミネストローネは、イタリア語で「具だくさん」などの意味があり、イタリアではトマト・ズッキーニ・さやいんげん・米などを入れて作ります。今日のミネストローネには、ベーコン・玉ねぎ・とうもろこし・キャベツ・奈良県でとれた米を粉にして作られた米粉のマカロニが入っています。もっちりとした食感を楽しんでくださいね。
4月17日 水曜日 給食5回目
ご飯・牛乳・ハンバーグのてり煮・ちりめんキャベツ・わかめのみそ汁
今日は、「わかめ」の話をします。わかめは冬に種をまき、春に収穫します。わかめは
海そうの一つで、海に囲まれた日本では昔から海そうを食べる習慣があります。海そうには、ミネラルや食物せんいがたっぷり含まれていて栄養豊富であることから、「海の野菜」と呼ばれています。みなさんの食事の中にもすすんで「海そう」をとりいれましょう。今日のわかめのみそ汁も、おいしくいただきましょう。
4月16日 火曜日 給食4回目
パン・牛乳・ポークチャップ・キャベツのソテー・コンソメスープ
今日は、「ポークチャップ」の話をします。ポークチャップは、豚肉を炒めてトマトケチャップなどで味付けした料理です。アメリカの家庭料理である「ポークチョップ」をもとに、日本でうまれたメニューといわれています。味付けで使うトマトケチャップは、トマトや玉ねぎに、砂糖・酢・塩・香辛料などの調味料を加え、煮込んで作られます。また、給食のポークチャップは豚肉の他に、玉ねぎ・しめじも入っています。味わっていただきましょう。
4月15日 月曜日 給食3回目
ご飯・いわしフライ・きらずの煮物・奈良なめこのみそ汁・ミニたい焼き
今日は、「古都ならの日」です。奈良市で作られたお米をよりおいしく味わうために、地場産物や郷土料理を取り入れた献立が登場します。きらずの煮物は、奈良の郷土料理です。「きらず」とは、豆腐を作る時にできる、大豆をしぼった残りの「おから」のことです。おからは細かいので、包丁で切る必要がないということから、「きらず」と呼ばれるようになりました。おからは、おなかの調子をととのえてくれる食物せんいをたくさん含んでいます。奈良なめこのみそ汁には、奈良県の十津川村で特産品として栽培されている「なめこ」が入っています。奈良の郷土料理や食材を、味わっていただきましょう。
4月12日 金曜日 給食2回目
ご飯・牛乳・ビビンバ・トックスープ・大根キムチ
今日は、「ビビンバ」の話をします。ビビンバは、韓国料理の代表的なご飯料理の一つです。ビビンバは正しくは、「ビビムパム」といいます。「ビビム」は混ぜ合わせるという意味で、「パム」は、ご飯のことです。韓国の甘辛い味噌コチジャンやごま油などの調味料を使い味付けをした、肉やナムルをご飯と混ぜます。韓国では、ご飯の上に盛られる具は、5種類とされているそうです。給食では、豚肉・ほうれん草・にんじん・太もやし・切り干し大根の5種類の具が入っています。ご飯に混ぜていただきましょう。
4月11日 木曜日 給食1回目
減量パン・牛乳・ミートソーススパゲティ・ボイルサラダ・アセロラゼリー
今日から1学期の給食が始まりました。
今月のめあては、「給食の決まりを守ろう」です。食事の前には、石けんで手をきれいに洗いましたか。給食当番さんはマスクを鼻までかくれるようにつけましたか。直接食べ物に触れないように器具を使って配膳しましたか。食事中は大きな声でのおしゃべりは控えて給食をしっかり味わい、残さないように食べましょう。クラスみんなで決まりを守り、給食の時間を楽しく過ごしましょう。